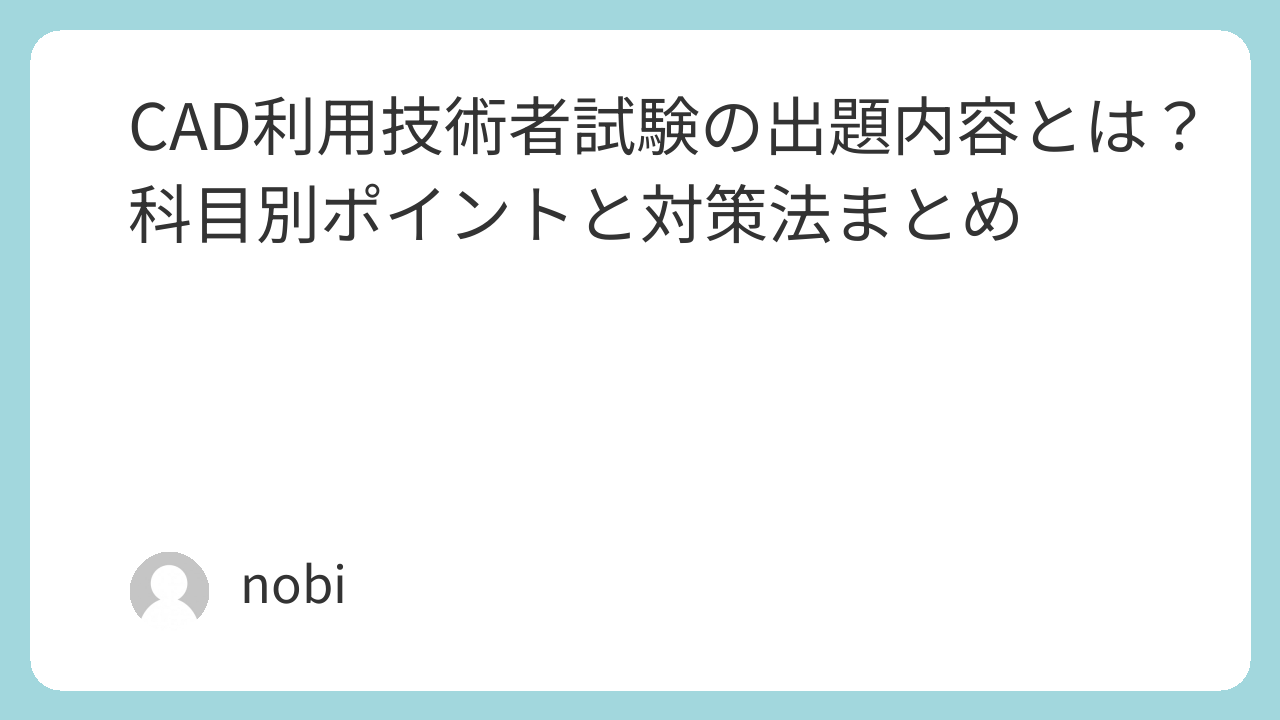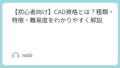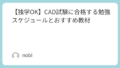CAD利用技術者試験に独学で挑戦しようとしている方にとって、「試験ではどんな問題が出るの?」「どこを重点的に勉強すべき?」という疑問はつきものです。
この記事では、出題範囲を科目別にわかりやすく整理し、初心者でも安心して対策できるようにポイントと勉強法を丁寧にまとめています。
独学でも合格できる力をつけたい方は、ぜひ参考にしてください。

IT/機電のフリーランス案件をお探しならエンベスト
CAD利用技術者試験とは?試験の概要をおさらい
まずは、CAD利用技術者試験の基本的な情報や種類を確認し、出題範囲を正しく理解するための土台を作りましょう。
どんな資格?実施団体と試験の種類
CAD利用技術者試験は、一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)が主催する民間資格です。
CADを使った設計や製図の基本的な知識・技能を評価するもので、建築・製造・機械・電気など多様な業界での活用が想定されています。
初心者から上級者までを対象とした3つの試験区分が用意されており、自分のレベルに合った内容からステップアップしていくことができます。
基礎・2次元・3次元の違い
CAD利用技術者試験は以下のように分類されています:
- 基礎試験:CADに関する基礎知識、パソコンリテラシー、操作概念などを問う初心者向けの筆記型試験(CBT形式)
- 2次元CAD試験:2D図面作成に必要な知識と操作スキルを評価。実技試験+選択式問題が中心
- 3次元CAD試験:立体設計に関する操作知識と3DCADの理解が求められる上級者向け試験
独学で学び始めた方が最初に挑戦するのは、基礎試験が圧倒的に多く、続いて2次元CAD試験へと進む流れが一般的です。
試験方式(CBT)と受験の流れ
現在、CAD利用技術者試験の多くはCBT(Computer Based Testing)方式で実施されています。
これは、全国のテストセンターでパソコンを使って解答する試験方式で、紙とペンではなくマウスとモニターを使用して解答します。
試験日は受験者が自由に選択できるため、学習スケジュールに合わせて柔軟に対応可能です。
申込は公式サイトから行い、会場や日程の空き状況を確認しながら予約する流れとなります。

出題範囲の全体像|カテゴリと問題構成を把握しよう
ここでは、CAD利用技術者試験の出題内容を大まかに把握できるよう、カテゴリごとの全体像や出題傾向を紹介します。
出題カテゴリの一覧(全体マップ)
CAD利用技術者試験の出題範囲は、次のようなカテゴリに分類されています:
- 製図の基礎知識:尺度、図形、線種、図面のルールなど
- CADソフトの基本操作:レイヤー、作図、編集、画層設定
- 図面表現の理解:寸法、投影法、断面図、アイソメ図など
- ハードウェア・ソフトウェア知識:PCスペック、OS、プリンタなど
- ファイル管理・データ交換:DWG・DXF・PDFなどのファイル形式
- セキュリティ・著作権:情報管理、ライセンスの基本
このように、設計の基礎知識とパソコン操作スキルがバランスよく問われる構成になっているのが特徴です。
科目別の出題割合と特徴
CAD利用技術者試験の出題は、カテゴリごとにバランスよく構成されていますが、特に頻出となる科目には傾向があります。
基礎試験の場合、以下の3カテゴリが特に重要です:
- 製図の基礎知識:全体の25〜30%
- CAD操作の基本:20〜25%
- 図面表現の理解:15〜20%
これらで全体の約7割を占めており、得点源として重点的に対策すべき領域といえます。
ハードウェア関連、ファイル形式、著作権や情報管理などは10〜15%程度で、補足的な知識として押さえておくと良いでしょう。
まず押さえるべき基本用語とは?
初心者がつまずきやすいのが、製図やCADソフトに特有の専門用語です。
以下のような言葉は、出題頻度が高く、正確に理解しておくことが重要です:
- 尺度(スケール): 実際の寸法と図面上のサイズ比率。例:1/100=100分の1サイズで図示。
- レイヤ(画層): 図面内で情報を分類・管理するための層。建物図面では「壁」「窓」「家具」などに分けて使う。
- トリム: 線を指定位置で切断するコマンド。編集作業で多用される。
- フィレット: 角に丸みをつける処理。製造図面などで多用される。
- DWG/DXF: CAD図面の代表的なファイル形式。DWGはAutoCAD専用、DXFは他ソフトとの互換用。
- ビューポート: レイアウト画面でモデル空間を表示する枠。印刷範囲の設定に使われる。
これらの用語は単なる暗記ではなく、具体的な操作イメージとセットで理解すると記憶に残りやすくなります。
特に図面作成や編集のプロセスを意識しながら、用語の意味を確認していきましょう。

CAD資格も活かせる!IT/機電のフリーランス案件をお探しならエンベスト
【図解表付き】出題カテゴリとその内容まとめ
ここでは、試験で出題される各カテゴリの内容について、初心者にもわかりやすく具体例とともに解説します。
さらに、視認性の高いHTML表を使って内容を整理していますので、出題傾向を効率よく把握するのに役立ててください。
製図の基本(尺度・線の種類・投影法など)
「製図の基本」は、試験の根幹ともいえる重要分野です。
ここでは、設計図を描くうえで欠かせないルールや記号、尺度の考え方、線種、投影法の種類などが問われます。
例えば、第三角法と第一角法の違いを図面から読み取る問題や、2つの図面の比較による正誤判定などが出題されます。
初心者はまず、「投影法」「断面図」「寸法記入ルール」などの基本を学習し、実際の図面を見ながら理解するのが効果的です。
CADソフトの基本操作(メニュー・レイヤ・ショートカット)
操作に関する問題では、「このアイコンは何の機能か?」「画層を正しく設定するには?」といった問題が出題されます。
特に、AutoCADやJw_cadでよく使われるコマンド名やショートカット(例:TRIMやOFFSET)は暗記しておくだけで得点に直結します。
実際にソフトを触りながら、よく使うコマンドはショートカットキーと一緒に覚えると効率が良いでしょう。
ファイル管理・データ交換(PDF、DXF、DWGなど)
ファイル形式に関する問題は、意外と盲点になりやすい分野です。
たとえば、「DXF形式とDWG形式の違い」や「PDF出力時に設定するべき項目」など、実務に近い知識が問われます。
また、保存先の設定や、他の設計者とのデータのやり取りで起きるトラブル(例:バージョン違いで開けない)といった、現場でよくある問題の対応方法も出題されます。
【カテゴリ別まとめ表】
| カテゴリ | 出題される内容 | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 製図の基本 | 尺度、線種、寸法、投影法 | 図面例で用語を確認し、記号と意味をセットで暗記 |
| CAD操作 | コマンド、レイヤ管理、ショートカット | 実際にソフトで操作しながら覚える |
| ファイル管理 | DWG/DXF/PDFなどの形式、保存方法 | 形式ごとの用途と変換操作を確認 |
| 図面表現 | 図形の種類、寸法表記、断面図 | 投影図や断面図の例を数多く見る |
| ハードウェア | PC性能、ディスプレイ、入力機器 | スペック名や役割を把握(RAM、GPUなど) |
| セキュリティ | 著作権、ライセンス、情報漏洩対策 | CADデータの保存・共有時の注意点を理解 |
初心者がつまずきやすいポイントと克服法
独学で試験に取り組む方がよくつまずくポイントを3つ取り上げ、それぞれの克服法を解説します。
よくある用語ミスと混同しやすい概念
たとえば「尺度」と「縮尺」を混同したり、「線種」と「レイヤ」の違いがあいまいになっているケースは非常に多いです。
これは実際の図面や操作経験が少ないことが原因です。
そのため、用語は意味だけでなく「具体的にどんな場面で使うのか」とセットで覚えるのが効果的です。
図面の読み取り問題の解き方コツ
図面を読み取って答える問題では、寸法記入ルールや第三角法の読み違いがよく起こります。
断面図の向き、投影図の位置関係などを「パズル」のように見立てて解いていく力が必要です。
対策としては、解説付きの問題集を活用し、「なぜその答えになるのか」を理解しながら進めましょう。
操作系の理解に必要な実機体験
知識問題だけではなく、操作系の出題(特に2次元試験以降)では、実際にCADソフトを使って図形を描く練習が不可欠です。
Jw_cadやAutoCADの体験版をインストールして、練習図面を真似して描いてみると、コマンドの意味やミスしやすい点が実感できます。
効率よく対策するための勉強法
時間に限りがある中で、出題範囲全体をカバーするには「優先順位」と「アウトプット重視の学習」がカギになります。
カテゴリごとの優先順位をつけよう
最初に行うべきは、出題割合の高いカテゴリから対策を始めることです。
製図の基礎 → CAD操作 → 図面表現の順で進めれば、効率よく合格ラインに近づけます。
「全体を完璧にしよう」とせず、出題比率に応じて得点源を作ることが重要です。
過去問・模試を活用したアウトプット学習
知識の定着にはインプットだけでなくアウトプットが必須です。
市販の問題集や模試を使って、実際の出題形式に慣れておくことで、試験当日の緊張感にも対応できます。
また、間違えた問題は「なぜミスをしたのか」をノートにまとめておくと復習効果が高まります。
おすすめの教材・サイト・アプリまとめ
独学者向けにおすすめの教材・ツールをご紹介します:
- 公式サイトのサンプル問題(ACSP公式)
- 市販本:『よくわかるCAD利用技術者試験公式ガイド』
- スマホアプリ:「CAD試験対策(選択式問題演習)」など
- Jw_cad練習用の無料図面配布サイト
教材は1つに絞らず、紙+デジタル両方を併用することで、記憶の定着と効率が向上します。
【表で確認】出題範囲別の対策ポイントまとめ
ここでは、各カテゴリの出題意図と、対策方法を一覧でまとめた表をご紹介します。
効率よく対策するための優先順位・学習手段・理解の深め方などを一目で確認できます。
出題科目ごとの重要度と対策法
| カテゴリ | 出題比率 | 重要度 | 対策法 |
|---|---|---|---|
| 製図の基礎 | 約25〜30% | ★★★★★ | 用語理解と図面例で実感する |
| CAD操作 | 約20〜25% | ★★★★★ | ソフトを使って練習 |
| 図面表現 | 約15〜20% | ★★★★☆ | アイソメ図・断面図を読む練習 |
| ファイル管理 | 10〜15% | ★★★☆☆ | 形式ごとの用途を理解 |
| ハードウェア | 10%前後 | ★★☆☆☆ | 用語暗記中心 |
| セキュリティ | 10%未満 | ★★☆☆☆ | 著作権・情報管理の基本理解 |
理解・暗記・操作のどこを伸ばすか?
試験では「理解して覚える」領域と「操作に慣れる」領域が明確に分かれています。
学習バランスとしては:
- 理解重視(製図・図面読解):理論と実例をセットで学習
- 暗記重視(用語・形式):頻出用語を集中してインプット
- 操作重視(CAD機能):ソフトを実際に使ってコマンド練習
それぞれの目的に応じて、最適な学習方法を選ぶことが合格の近道です。
短期集中学習の具体的なスケジュール例
2週間〜1ヶ月で合格を目指す場合の例:
- 1週目:用語の暗記+製図知識の理解(毎日30分)
- 2週目:CAD操作の実践(Jw_cadまたはAutoCADを使って簡単な図面作成)
- 3週目:模擬試験・過去問演習(1日2セット)+間違い分析
- 4週目:弱点補強+試験当日のリハーサルと環境確認
毎日の積み重ねが大きな力になるので、「完璧を目指さず確実に進める」ことを意識しましょう。

まとめ|出題範囲を理解すれば、合格ラインは見えてくる
CAD利用技術者試験は、出題範囲が幅広いものの、各カテゴリごとに明確な対策が存在する試験です。
特に初心者や独学者にとっては、どこから始めればよいか不安になるかもしれませんが、出題割合の高い分野を優先的に学習し、基本用語と図面読解をしっかり押さえることで、合格は十分に狙えます。
時間をかけるよりも、戦略的に勉強することで、効率よく実力を伸ばせるのがCAD試験の良さです。
まずは出題範囲を俯瞰し、自分に必要な知識・スキルを明確にして取り組んでいきましょう。
チェックリスト:勉強開始前に確認したい項目
- 出題カテゴリを把握しているか?
- 用語や操作コマンドの基本を押さえているか?
- 製図の尺度や線種などを理解しているか?
- CADソフトを使って簡単な図面が描けるか?
- 過去問や模擬問題で演習を行ったか?
- 試験の流れ・形式(CBT)を確認したか?
- 学習スケジュールに無理がないか?